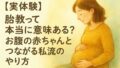「またゲームばっかり…」「いい加減、勉強しなさい!」
そんなふうに毎日声をかけては、自己嫌悪。
できれば「勉強しなさい」と言わずに過ごせたら……そう思いませんか?
実は、子どもが自然と机に向かう家庭には、共通点があります。
東大・京大出身者に共通する「言われなかった」育て方
私が接した難関大学に合格した学生の多くは、
「親から勉強しなさいと言われた記憶がない」と答えています。
なぜでしょうか?
それは、勉強が楽しいことだと自然に思えたから。
親からの圧力ではなく、好奇心や自己肯定感を育てる環境が整っていたのです。
賢い子が育つ家庭の4つの習慣
ここでは、私自身の子育て経験と、教育現場で見てきた子どもたちを通して感じた
「賢く育つ家庭習慣」を4つご紹介します。
① 「あなたはできる子」と信じて接する
子どもは、親のまなざしを通して自分を見ています。
「あなたならできるよ」「すごいね、やってみよう!」
そんな言葉を繰り返すことで、「自分はできる存在だ」と思えるようになります。
これは“ピグマリオン効果”と呼ばれ、
親の期待が子どもの力を引き出す心理現象として知られています。
② 「なんで?どうして?」にできるだけ応える
小さな子どもの「なんで?」「どうして?」は、すべて学びのはじまり。
忙しいときでも、
- 「それ面白いね」
- 「あとで一緒に調べようか」
と返すことで、好奇心が育ちます。
質問に前向きに向き合う姿勢が、
やがて「自分で調べてみよう」という自発的な学びにつながるのです。
③ 集中しているときは静かに見守る
子どもが夢中で遊んでいるとき、
つい「ご飯よ〜」と声をかけていませんか?
でも実は、この“夢中の時間”こそが学びの力を育てる時間。
本を読んでいるとき、ブロックで黙々と遊んでいるとき……
その集中力を邪魔しないことで、
自分で物事に取り組む「主体性」や「思考力」が育っていきます。
④ 遊びや体験こそ最高の学び
勉強は、机に向かうだけではありません。
- おままごと →「順番」「会話力」
- レゴブロック →「空間認識」「創造力」
- お菓子作り →「計量」「手順」「失敗の経験」
こうした五感を使った遊びや体験が、
小学校以降の「思考の土台」になります。
「遊んでばかりで…」と思わずに、
今だけの“学びのチャンス”として見てあげてくださいね。
「天才」にしようとしなくていい
「この子を賢く育てたい!」と思うのは自然なこと。
でも、「なんでできないの?」と焦ってしまうと、
勉強=つらいものになってしまいます。
目指すのは、“天才”ではなく、
「学ぶことが好きな子ども」。
「わからないこと」にワクワクできる子は、
どんな道に進んでも、学び続けられる力を持てるのです。
まとめ|“学びたい”は、子どもへの最高のプレゼント
賢い子に育てるために、特別な教材や習い事は必要ありません。
今日からできる小さな習慣の積み重ねが、
子どもの未来をつくっていきます。
家庭でできる4つの習慣まとめ
- 子どもを「できる子」と信じて接する
- 「なんで?」に前向きに応える
- 夢中になっている時間を静かに見守る
- 遊びや体験を“学び”と捉える
私も、子どもが静かに本を読んでいるとき、
声をかけたい気持ちをグッとこらえてそっと見守っていました。
あの時間こそが、学びの種まきだったと思います。
「勉強しなさい」と言わずに、
“学ぶって楽しい”と思える環境を一緒に作っていきませんか?